情報通信ネットワーク安全・信頼性基準、信頼性試験、故障率について
(1)情報通信ネットワーク安全・信頼性基準(昭和62年郵政省告示第73号)及び附則(平成25年総務省告示第134号)について
情報通信ネットワーク安全・信頼性基準は、情報通信システムにおける安全・信頼性対策全般にわたり、基本的、かつ、総括的な指標を示すものである。本基準は、全部で123項目276対策からなっており、設備及び設備を設置する環境の基準である【設備等基準】と、設計、施工、維持及び運用などの基準である管理基準とに区分されている。
このうち、管理基準は、ネットワークの設計管理、施工管理、保全・運用管理のほか、設備の更改・移転管理、情報セキュリティ管理、【安全衛生】管理、環境管理、防犯管理、非常事態への対応、教育・訓練、現状の調査・分析及び改善、安全・信頼性の確保等の情報公開、電気通信事業者の取組等など広い範囲に及んでいる。
これら管理基準のうち、ネットワークの設計管理、施工管理及び保全・運用管理に関する項目は19項目あり、それらの項目は下表のとおりである。

(2)信頼性などについて
(ⅰ)信頼性試験について述べた次の文章のうち、誤っているものは、【②】である。
①実使用状態でアイテムの動作、環境、保全、観測の条件などを記録して行う試験は、一般に、フィールド試験(現地試験)と言われる。
②【限界試験とは、使用できる限界を確かめるために行う試験。保全中に非破壊的に行う場合がある。】
③アイテムに対して等時間間隔でストレス水準を順次段階的に増加して行う試験は、一般に、ステップストレス試験と言われる。
④加速試験における加速手段として、ストレスを厳しくして劣化を加速させる方法、負荷の間欠動作の繰り返し度数の増加や連続動作による時間的加速を図る方法などがある。
メモ:
デイペンダビリティ(信頼性)用語
http://kikakurui.com/z8/Z8115-2000-01.html
(ⅱ)信頼性抜取試験について述べた次の文章のうち、誤っているものは、【④】である。
①信頼性抜取試験では、一般に、大量生産品ではロットから、生産量の少ない品目の場合にはアイテム集団から任意抽出したサンプルについて、故障率などの信頼性を調べた結果に基づき全体の合否判定を行う。
②抜取方式には計数型と計量型があり、寿命時間を観測して合否判定を行う方式は、計量型方式に分類される。
③1回だけ抜き取ったサンプル中の故障件数のデータを観測して合否の判定を行う方式は、一般に、計数1回抜取方式と言われる。
④信頼性抜取試験の結果、合格水準であるロットが不合格になる確率は【生産者危険率】と言われ、不合格水準である悪いロットが合格となる確率は【消費者危険率】と言われる。
メモ:
統計−用語と記号−第 2 部:統計的品質管理用語
http://kikakurui.com/z8/Z8101-2-1999-01.html
(3)10000個のメモリ素子を組み込んだ基盤Aの信頼性について。ただし、基盤Aは偶発故障期間にあるものとし、loge0.99=-0.01、e-0.05=0..95とする。
基盤Aの使用開始後100時間における信頼度が0.99であるとき、メモリ素子1個の故障率は、【10】〔FIT〕である。また、基盤Aの使用開始後500時間以内に故障する確率は、【5】〔%〕である。ただし、メモリ素子個々の故障率は同一値とする。
メモ:
偶発故障期間(CFR):
初期故障期間(DFR)と摩耗故障期間(IFR)の間の故障率が一定(λ)の期間。
FIT(Failure rate):
電子部品などの場合、故障率(λ)の低減につれて小さな単位へと移行してきたため、現在では、109時間を1単位として表すようになりここで用いられる1単位が〔FIT〕となる。
故障率に109をかければ算出できる。
信頼度R=e-λt
0.99=e-λ×100
loge0.99=-0.01のため、0.99=e-0.01であるため
(0.99=e-λ×100)=(0.99=e-0.01)となり
100λ=0.01 λ=0.0001となる。
これは10000個の故障率となるため、メモリ素子一個の故障率は
λ=0.0001×0.0001=0.00000001=10-8
10-8×109=10〔FIT〕
次に500時間稼働した際の故障確率を求める。
信頼度R=e-0.0001×500=e-0.05=0.95
故障確率F=1-信頼度Rであるため、
故障確率F〔%〕=0.05×100=5〔%〕
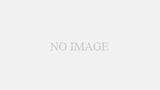
コメント